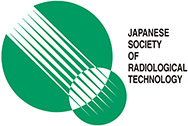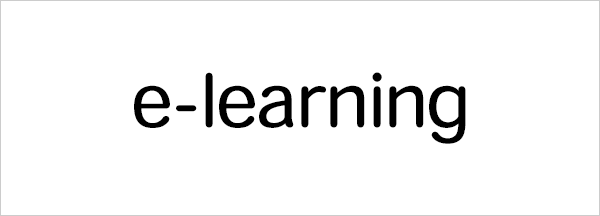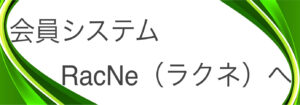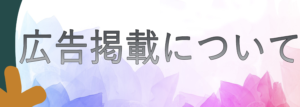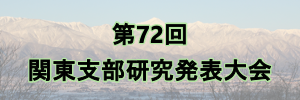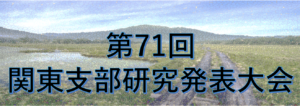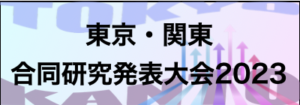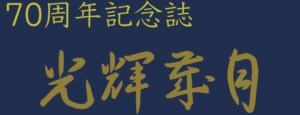関東支部のご案内
- ホーム
- 支部役員からの挨拶
支部役員からの挨拶
「関東支部会員のための関東支部事業運営」
関東支部 支部長 柳田 智(つくば国際大学)
2023年度より、日本放射線技術学会関東支部長を拝命いたしましたことを、支部会員の皆様に心よりお礼申し上げます。平野元支部長、梁川前支部長の意思を引き継ぎつつ、支部理事や研究会幹事の皆様と支部会員のために尽力してまいりたいと思いますので、ご協力のほどをよろしくお願いいたします。支部長就任にあたり、以下のことを目標として事業を進めてまいりたいと思っております。
①論文投稿の促進
学術活動において、エビデンスを残すためにも論文投稿は重要です。関東支部にはCTGUM、関東RT研究会、関東DR研究会、関東MR研究会、関東angio研究会、関東核医学研究会の6つの研究会があります。研究会には各専門領域のプロフェッショナルな幹事がいます。各研究会は年間を通して会員の皆様に研究に有用な情報をセミナーを通じて発信しております。さらには,自宅からも参加しやすいWebnerやハイブリッド開催のセミナーを行っております。会員の皆様にはセミナーに積極的に参加していただき、幹事と交流し、日頃の研究成果を論文投稿して発表していただければと思います。
②人材育成
会員の皆様に支部の活動を知っていただくことは、開かれたJSRTを知るためにも重要なことだと思っています。また、支部事業に若い方々が協力していただき、活躍いただくことも、役員の若返りや後輩の育成につながると思います。私は若い会員の方々に積極的に事業に参画していただくようお願いしたいと思っています。そのためにも、関東支部研究発表大会や各研究会のセミナー等に参加していただき、新旧役員と交流を持っていただくことにより、支部事業で活躍していただく機会が増えると思います。是非とも多くの方々の参加をお待ちしております。
③新入会員の入会促進と現会員へのサービス向上
各県ブロックには、優秀な人材がいるにもかかわらず、JSRTや関東支部への催しへの参加が鈍い拠点医療施設があります。また、中小医療施設においても、JSRTや関東支部の存在すら知らない診療放射線技師もいます。コロナ禍において、会費負担が生活を圧迫し退会や除名になる会員も多くいます。JSRT正会員の入会促進をどのようにすればよいか、また現会員にとってどのような事業がサービス向上につながるかを、支部理事や研究会幹事の方々と考えてまいりたいと思います。
④70年70回記念事業
本年度は研究発表大会の70年70回記念の年になります。30回では、東京支部と合同で記念誌を発刊しております。50年50回では関東支部独自でDVDを発刊しております。今年度は年度予算計上や東京・関東合同研究発表大会2023が開催されるため、記念事業は見送りたいと思いますが、次年度開催に向けて準備委員会を発足いたします。現在のところ、会員の皆様には電子化したデータの発刊配布を予定しております。是非とも発刊配布を楽しみにお待ちいただければと思います。
以上の4点を重点に、支部長として支部運営に尽力してまいりたいと思います。支部会員の皆様には支部事業にご参加いただきながら、JSRT関東支部へのご支援ご協力をお願い申し上げます。

「学術活動に参加しよう!」
関東支部副支部長 武井 宏行(つくば国際大学)
公益社団法人日本放射線技術学会関東支部の会員の皆さま,平素より支部活動にご理解・ご協力いただき,感謝申し上げます.
日本放射線技術学会は会員数を増加させ,論文を量産することでその時々の医療のエビデンスを創り上げる使命を持った学術団体です.そして関東支部は本部事業の方向性を活かし,関東独自の会員の皆さまへの様々なサービスを行っています.
学術講演会では医療安全,倫理教育などの総合的な内容からその時代の最先端の情報,また各モダリティのトピックスなどを提供してきています.研究発表大会は8県持ち回りで,地元の特色を活かした企画や東京支部との合同大会も行い,研究初学者へのサポートも行っています.また年度ごとに研究助成金の選考も行われています.論文作成のアシストとして前群馬県民健康科学大学学長の土井邦雄先生の講義と個人指導を行う「研究発表TERAKOYA」も行っています.
会員の皆さまへの敷居を低くしてお待ちしておりますので,ぜひ講演会やセミナーなどへのご参加をお願いするとともに,一緒に関東支部を創り上げていただければ幸いです.
「きほんのキホンの基本と人“考”知能の活用」
関東支部副支部長 相川 良人(山梨大学医学部附属病院)
公益社団法人日本放射線技術学会関東支部の会員の皆さま,平素より支部活動にご理解・ご協力いただき,感謝申し上げます.関東支部はより会員の皆様に近い位置での様々なサービスを提供しています.関東支部にある6つの研究会では,ビギナー向けの基本から最先端の情報や各モダリティのトピックスを提供し,研究発表大会では毎回テーマに沿った特色のある企画や会員の発表が行われます.研究初学者へのサポートは,支部研究助成や研究発表TERAKOYAも実施しています.
「きほんのキホンの基本」を合言葉に若手の研究者の育成に力を入れることを考えています.また,学術団体としてエビデンスの創造に力をいれ,数多くの論文が輩出できるような情報発信と放射線技術学を高めるため,関東支部役員,研究会メンバーが考えて作り上げた(人“考”知能の活用)各種事業の有効利用により,関東支部の学術活動の活性化を役員一同,会員の皆様と一緒に進める予定です.
会員の皆さまのご意見や希望を積極的に取り入れ,支部の事業に反映させたいと思っています.さらに,有益な情報を提供し,社会に貢献する団体を目指して,会員の皆さまと共に活動を展開していきたいと考えています.
“きほんのキホンの基本”から未来へ
― 関東支部が描く次のステージ ―
関東支部副支部長 飯森 隆志(千葉大学医学部附属病院)
日頃より関東支部の活動にご理解とご協力を賜り,心より御礼申し上げます.
関東支部は,放射線技術学の発展と会員の研鑽の場として,常に「きほんのキホンの基本」を理念の中心に据え,活動を展開してまいりました.基礎の習得なくして応用は生まれず,応用の積み重ねの先に革新があります.この理念は,先人たちが築いてきた学術的土壌の中で育まれ,今も私たちの活動の根幹を成しています.現在,放射線技術を取り巻く環境は加速度的に変化しています.AIやDXといった新しい潮流の中で,診療放射線技師に求められる知識やスキルも高度化・多様化しています.こうした時代においてこそ,「基本に立ち返ること」「基礎を深めること」がより重要であり,それが新しい技術への対応力や研究力の土台となります.
関東支部では,CTGUM・DR・RT・MR・Angio・核医学といった各分野の研究会やセミナーを通じて,初学者から上級者まで幅広い層が学べる機会を提供してきました.近年では,Web配信やオンデマンド講義,対面とのハイブリッド形式を取り入れ,多様な学びのかたちを模索しながら活動を継続しています.その一方で,画面越しでは得られない交流や討論の場もまた,学会活動の大切な価値であり,今後も「人と人とのつながり」を大切にした事業の展開を心がけてまいります.こうした活動の中でも,特に力を入れているのが「若手研究者の発掘と育成」です.関東支部独自の人材育成事業である「研究発表TERAKOYA」は,研究活動の第一歩として,また臨床における疑問を“論文”という形に昇華させるための場として,多くの若手技師に活用されています.少人数の合宿形式による密度の高い指導は,受講生だけでなく,支援する側にとっても学びの多い時間となっています.今後も「研究発表TERAKOYA」を中心に据え,論文作成や学会発表を支える仕組みを強化していきます.また,関東支部として,若手の論文投稿を後押しする新たな取り組みも進める予定です.研究発表大会での優秀演題に対する論文化支援や,和文誌投稿への橋渡しを行うことで,発表から論文へ,そして発表者から研究者へのステップアップを後押ししていきます.あわせて,これに伴う研究助成金制度の見直しも検討し,より実効性のある支援体制の整備を進めてまいります.研究は特別な誰かが行うものではなく,臨床に向き合うすべての診療放射線技師に開かれた「知の追究」です.関東支部では,そうした「研究の敷居」を少しでも下げ,多くの若手が自らの問いに向き合い,発信していく機会を創出してまいります.70年の歩みを経た関東支部は,次の100年に向けてさらなる進化が求められています.関東支部の活動は,役員や幹事だけが担うものではなく,一人ひとりの会員によって形作られるものです.皆様の知識,経験,そして情熱こそが,放射線技術の未来を照らす原動力となります.
今後も関東支部は,「基本を学び,研究を楽しみ,人を育てる」ことを大切にしながら,会員の皆様と共に歩んでまいります.引き続きご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます.